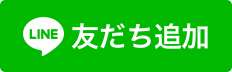軽視厳禁!加齢による筋量減少と骨密度低下のケアと対策

中高年の常套句「体力落ちた~」を具体的に可視化しよう
年齢を重ねると共に、何かと体の不自由さを感じるようになって来るのが加齢。
体のあらゆる機能が低下・劣化していくことは周知の事実で、外見的な変化はもちろん、内臓機能から骨格筋まで様々な部位・器官が影響を受けます。ただし加齢においては、外見変化以外あまり実感が湧かないのも実情で、一気に各部の機能が低下する訳ではなく、日常生活のなかで
溶け込むように加齢症状が順応していく
ことから、具体的に加齢による機能低下に対して対策を行っている人は限られ、基本的にエイジングケアというと、スキンケアなどを主体とした外見変化の対応に留まっているのが実情かもしれません。
そんななか、加齢による機能低下を実感させるのが、
「体力落ちたな~」という場面
特に中高年ともなると、あらゆる日常生活のなかで感じる頻度が多くなる傾向にあり、例えば通勤途中の駅の階段、主婦の方ですと布団を干したり仕舞ったりする場面などが挙げられ、体力の衰えや疲れやすさを実感するだけでなく、それがストレスになったり、生活の質そのものを低下させるリスクもあります。
そんな中高年の常套句でもある「体力が落ちた」という認識ですが、もちろんその感じ方については個人差が大きい部分ではあるものの、事実として
本当に体力は落ちているのか?
という問題もありますし、
そもそも「体力」とは何を指しているのか?
という点は意外と抽象的。感覚的に体力が落ちたと感じていても、実は単に疲れているだけかもしれませんし、中年太りで体が重くなっているだけかもしれませんので、本当に体力が落ちているのかを数値化・可視化できれば、よりインナーケアの重要性の認識も高まることになります。
そこで今回の記事では、そんな中高年の口グセでもある
「体力落ちたな~」を可能な限り可視化し
年齢と共に減少する筋肉量の変化や、骨密度の減少量を数値的に把握する方法についてピックアップしていきます。実はこの「体力落ちた」は、加齢によって多くの方が実際に機能低下に見舞われているのが実情ですが、当然日々の運動習慣によって
ある程度機能低下を抑制することができる
わけで、例えば80代の人でも、60代の骨格筋を維持している人も決して珍しいわけではない一方、逆に40代でも60代くらいの筋量しかないというケースも少なくありません・・・これはかなりショックですよね?!
今回は、そんな体力低下の主な要因となる筋量変化と骨格変化を数値化する方法について詳しくご紹介していきます。そうした加齢変化を把握することで、外見的なエイジングケアだけでなく、体の中から健康を維持するための具体的なインナーケアについても取り上げていきます。
30歳をピークに10年で5%?!サルコペニアはなぜ起こる?

さて、具体的に加齢に伴う筋量低下について見ていきましょう。
加齢によって筋量が減少するメカニズムにおいては、過去記事「▼2023年後半の健康テーマは「ロコモ対策」~そもそもロコモとは?」でも詳しく取り上げておりますが、端的に言うと
運動不足などで筋繊維への刺激が減り筋肉も委縮する
からで、程度の違いはあれど筋肉量の減少(サルコペニア)は避けられないと言っても過言ではありません。さらに
筋肉量が減少するとどうなるの?
という点においては、見た目の体型変化はもちろんのこと、
1,基礎代謝の低下
エネルギー消費量が減少して太りやすくなる、生活習慣病リスクが高まる。
内臓脂肪が溜まりやすくなり、糖尿病やガンのリスクも・・・
2,運動機能の低下
筋肉量が減少することで筋力不足となり、歩行が遅くなったり階段がキツくなる。
高齢者などは転倒のリスクも高まる
3,骨および関節への負荷増加
筋量が減少することで骨や関節への負荷が増える。
骨折や関節痛だけでなく、骨粗しょう症などの原因にもなる
といった弊害を生じさせます。
その他にも、尿漏れの原因ともなる骨盤底筋群の劣化、腹直筋や腹斜筋が弱ることで便秘になりやすくなったりと、筋力低下に伴う様々な健康リスクが高まります。前述のとおり、加齢による筋量低下は避けられないのですが、実際の筋量減少ペースにおいては
- 20代で筋肉量のピークを迎える
- 30歳ごろから緩やかに減少し始める
- 40代以降は、10年ごとに約3~10%程度減少する
- 60代以降は減少ペースが速まり、10年で約8~15%減少
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/
0000209720.pdf
つまり、単純計算すると、20代の時のピーク筋量と比較して
70代までで最大40%前後も筋量が減る可能性
があることが明らかになっています。
自分の体の筋肉が40%も減るというイメージがまったく湧きませんが、例えばご自宅にある体組成計などで、体脂肪率や骨格筋率を計ってみれば一目瞭然。特に、体のなかでも大きい筋肉で、歩く・しゃがむなどの下肢の運動機能を司る
大腿四頭筋は筋量減少のピッチが速い
傾向にあり、ゆえに高齢になるほど歩行困難になる人が多くなるのです。
なお、加齢による筋肉量の減少をサルコペニアと呼びますが、単なる筋肉量の減少だけに留まる場合はプレサルコペニア、運動機能の低下が顕著であればサルコペニアに該当することになります。
さすがに40代で筋肉量の減少は見られないかもしれませんが、40代後半から50代以降はサルコペニアが顕著となってきますので、エイジングケアを意識するのであれば「筋肉量の維持」を第一に心掛けることが重要。つまり
運動によって筋肉に刺激を与えて筋肥大を図る
ことによって代謝があがり、内臓脂肪の蓄積も抑制、骨や関節への負荷増も抑えられるようになります。決して加齢による筋肉や骨格の劣化を侮ってはならないということを覚えておくようにしましょう。
「中高年の体力低下」に関する人気記事
骨密度もDXA法で数値化!特に下肢機能の劣化を抑制しよう

続いては、筋量低下と密接な関係にある骨密度(BMD)です。
骨密度と聞いてもあまりピンと来ないかもしれませんが、前段で触れましたように、筋肉と骨は互いに刺激し合っており、互いの働きをサポートしています。
具体的には、筋肉は骨を刺激して「骨芽細胞」という細胞を活性化し、骨の新陳代謝を促して骨の強度を保っています。また、骨も「オステオカルシン」というホルモン様タンパク質を分泌して筋肉の働きをサポートしており、筋肉と骨は持ちつ持たれつの関係にあります。つまり、加齢による筋肉量の減少については、
- 筋肉量が減ることで骨への刺激も減る
- 骨への刺激が減ることで新陳代謝が鈍化
- 骨を作るサイクルが鈍化することで骨密度も低下
というのが、加齢による骨強度低下のメカニズムです。
ただ、さすがに働き盛りの40代で骨密度が顕著に低下する訳ではありませんが、前述のとおり、筋肉量のピークが20代であるのと同時に、
骨量(最大骨密度)も20~30代前半でピークを迎え
40代からは男女問わず徐々に減少していきます。
そんな骨密度の変化を数値化するのが、DXA法による骨密度の計測です。
DXA(Dual-energy X-ray Absorptiometry)検査とは、骨密度を測定する標準的な検査方法で、一般な病院やクリニックで検査可能です。日本では骨密度の指数を「YAM比(Young Adult Mean)」というパーセンテージで示されることが多く、その内訳は
若年成人の平均値に対して自身の骨密度の割合
となり、以下のような目安が一般的です
- 80%以上:正常
- 70〜80%未満:骨量減少(骨粗しょう症予備軍)
- 70%未満:骨粗しょう症
さらに年代別でこのYAM比の目安を見てみますと、男女で違いこそはありますが
- 40代:95〜100%前後
- 50代:90〜95%前後
- 60代:85〜90%(女性:70〜80%)
- 70代:60〜70%前後
- 80代:50〜60%前後
※閉経後の女性は80〜85%程度まで低下する場合がある
https://www.mhlw.go.jp/content/
10904750/001316479.pdf
上記のとおりで、60代以降は多くの方で骨粗しょう症のリスクが高まります。
過去記事「▼大切なのは健康寿命!いつまでも元気でいるためのロコモ対策」でも取り上げているように、加齢による筋肉量の減少は、体の中でも
特に大きな筋肉である下肢筋肉が多く減少
することで、歩いたり、走ったり、といった日常動作が困難になってきます。
サルコペニアは、男性より女性の方が早期に出やすいこと、高齢者における歩行困難比率も女性の方が圧倒的に多いことを考慮しても、
相対的な筋肉量とその維持が重要
であることは言うまでもありません。
つまり、日常的な運動によって筋肉を刺激し続け、筋肉が刺激されることで骨の生成サイクルも促進させるというのが、中高年以降における筋力と骨密度維持の重要なポイントになり、歩行困難など生活の質の低下を避けるためにも、50代以降からはウォーキングなどの適度な運動習慣を身に付けることが非常に大切なのです。
まとめますと
- 50代以降は誰しも筋肉量が減少する
- 60代以降は特に下肢筋肉の減少ペースが強まる
- それを抑制するためには筋肉を使うこと
- 筋肉を使わないと骨も劣化し骨粗しょう症のリスク
- 筋肉を増やす・骨を強化するための食生活も意識
という意識を持ち、いつまでも自身の意思で動く大切さを改めて実感していただければと思います。
特に50代以降の女性は、足裏や膝が痛くなったり、股関節が痛くなったりと、下肢機能に何かしらの悩みを抱える人が増える傾向にありますので、骨格筋にまつわる栄養素をしっかり取り、毎日1時間程度のウォーキングを継続するなど、下肢筋肉へ刺激を与え続けることを意識すると良いでしょう。
当サイトに掲載されている情報は、一般的な健康・医療に関する知識や生活習慣などの改善のヒントを提供することを目的としております。本サイトの情報は、診断・治療・処方を目的としたものではありません。体調や症状に関する判断は、必ず医師や薬剤師、管理栄養士などの専門医・専門家にご相談ください。 なお、本サイトの情報に基づく行動や判断によるいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。掲載情報は可能な限り最新かつ正確な内容を心がけていますが、予告なく変更・修正する場合がございます。