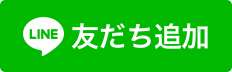【睡眠障害の4つの種類】種類別に見る原因と対処・改善策

多くの現代人の悩み「眠れない」を細分化した不眠改善アプローチ
現代人の多くの人が抱える身体の悩みのひとつ「不眠」。
不眠という言葉が持つ意味としては「睡眠が十分に取れずに何らかの支障が出ている状態」を指しますが、単に睡眠が十分に取れないといってもその症状や状態は多岐にわたることは説明の余地がありません。例えば、
- 眠りたいのになかなか寝付けない
- 寝ているのに途中で目が覚める
- ちゃんと寝ているのに寝た感じがしない
症状や状態は人や環境によって様々ですが、多くの人がこれらの総称として「不眠症」という言葉で一括りにしてしまいがちです。一般的に、眠れない状態や症状を不眠症と言ったり、睡眠障害という言葉を使いがちですが、これはあくまで総称であり、医学的な定義では
不眠症:十分な睡眠が取れずに生活に支障を来たしている状態
睡眠障害:良質な睡眠や睡眠時間の乱れなど睡眠に関連するすべての病態
となり、つまり不眠症は「睡眠障害のひとつ」ということになります。
睡眠障害の詳細については、過去記事「▼睡眠障害ってどんな症状?寝れない時の睡眠障害セルフチェック」で詳しく取り上げていますので、そちらを参考にしていただければと思いますが、例えばSAS(睡眠時無呼吸症候群)などは、ある意味ちゃんと寝ている(状況によりますが)ので、厳密には不眠症には該当しません。もう少し噛み砕いて分かりやすく言えば
眠れないという自覚そのものが主症状となるのが不眠症
とも言えるので、不眠対策を知るうえでは明確な不眠の区分を把握することが非常に重要ということを認識しておくようにしましょう。つまり、単に「眠れない」という抽象的な症状ではなく、
- なかなか寝付くことができない入眠困難なのか?
- 就寝中に何度も目が覚めてしまう中途覚醒なのか?
- 時間的にまだ寝れるのに目が覚めてしまう早朝覚醒なのか?
- ちゃんと寝てるつもりなのに疲れが取れない熟眠障害なのか?
それによって改善アプローチが違ってくることは言うまでもありませんので、不眠対策においては、自身がまずどのタイプに当てはまるのかをしっかりと把握する必要があります。
なお、不眠症の主な原因においては、
- 心理的要因(メンタル)
- 身体的要因(体の不調)
- 生活環境要因(体以外の要因)
- 高齢による深睡眠の減少
その他にも、服用している薬の影響なども挙げられますが、一般的には上記4つが主な要因となり、一つひとつの要因を深堀していくと、あらゆる要因が不眠のきっかけになっていることが分かります。よって、不眠の原因は人それぞれ固有の要因があり、その対策・改善方法においても
人それぞれ固有の対策・改善方法がある
ということを踏まえ、この記事では「【睡眠障害の4つの種類】種類別に見る原因と対処・改善策」と称し、それぞれの原因と対策・対処を状態・状況別に詳しく掘り下げて見ていきます。例えば、冷え性女性に多い「足先が冷えて眠れない」という不眠要因も、単に足先を温めれば良いという問題ではなく、
どのように足先を温めればスムーズな入眠を促せるか?
という点が重要であるとおり、その症状によっては生活習慣が大きく関わってくる可能性もあります。後述する内容となりますが、日本の睡眠事情は先進主要国のなかでもワースト1位であり、睡眠不足・睡眠の質の低下による日中の労働生産性の低下、それに伴う経済的損失は約15兆円※とも言われています。
出典:RAND Europe研究所
Why sleep matters — the economic costs of insufficient sleep
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1791.html
この機会に自身の不眠症状の理解を深め、日中に効率的・活動的に行動できるよう不眠を解消していきましょう。
日本の不眠による経済的損失は世界1位~日本社会が不眠要因?

現代社会においては、国を問わず多くの人がこうした不眠に悩んでいると考えがちですが、実はこの「不眠問題」は日本独自とまでは言えないものの、
日本だけが特に深刻で特殊な状態
であるということがデータから読み取ることができます。
前段のとおり、日本における睡眠不足を原因とした経済的損失が、GDP比約2~3%に相当する年間約15兆円が失われているとの調査結果があります。主要国でくらべてみると、
- 米国:約41億USD/年間
- 日本:約14億USD/年間
- ドイツ: 約600億USD/年間
- 英国:約500億USD/年間
額面だけで見るとアメリカが圧倒的に損失額が大きいのですが、GDP(国内総生産)に占める割合比率でみると
- 日本:2.92%
- 米国:2.28%
- 英国:1.86%
- ドイツ:1.56%
となり、日本が圧倒的に損失が大きいことが窺えます。
つまりこれはどういうことか?と言うと、誰しも一度や二度は「寝不足でダルい」とか、「睡眠不足でやる気が出ない」といった日を経験しているかと思いますが、
- 寝不足で仕事の効率が悪い
- 睡眠不足起因での仕事上のミス
- 寝不足による遅刻・欠勤
- その他もろもろ
こうした要因を背景に労働者全体レベルで、これだけの規模の経済損失が生じており、睡眠不足や睡眠の質低下が自分自身のみの問題ではないということが、数字上からも紐解くことができます。こうした数字を見ると、次に浮かんでくる課題が
なぜ日本だけが突出して損失が大きいのか?
という疑問が湧いてきますが、日本では古くから言われ、浸透している下記のような文化や価値観があり
- 日本人は勤勉な民族
- 残業することが責任感だったり、寝ないで頑張ることが美学
- 長時間労働が会社への忠誠心といった価値観
- 睡眠に対する意識が低く、寝る=怠慢という謎文化
といった、海外と比較するとかなり特殊な価値観が浸透していることも要因として挙げられます。逆に諸外国では「睡眠不足=自己管理ができていない」とマイナス評価される傾向にあり、こうした価値観や文化の違いが如実に数字として現れているのかもしれませんが、いずれにせよ
日本の不眠問題は日本社会全体の課題
と捉え、自身でも積極的に睡眠が取れるような環境を整えることが大切です。
特に社会人における不眠については、悩みや心配事といった心因的要因が大きい傾向にあり、仕事におけるプレッシャーや人間関係に対する悩みなど、人それぞれ個別で、解決しにくい様々な心因的要素が存在します。ただし、その「悩みの種」を解消しない限り不眠が解消されないという訳ではなく
不安や悩みを和らげる生活習慣や対処法
がないわけではありませんので、不眠要因がすぐに根本解決できないからといって、何も行動を起こさないのが一番の愚策にもなりかねません。
もちろん、病院にいって睡眠導入剤を処方してもらうというのも行動のひとつではありますが、まずは不眠要因となっている原因を自身でしっかりと把握し、そのために自身で何ができるかを検討してみることも問題解決の第一手となります。根本問題を解消できなくても、心因性不眠を解消する方法はいくつかありますので、次章にて詳しくご紹介していきます。
「睡眠障害の種類」に関する人気記事
個々のメンタルの問題?不眠原因を理解して改善策を講じよう
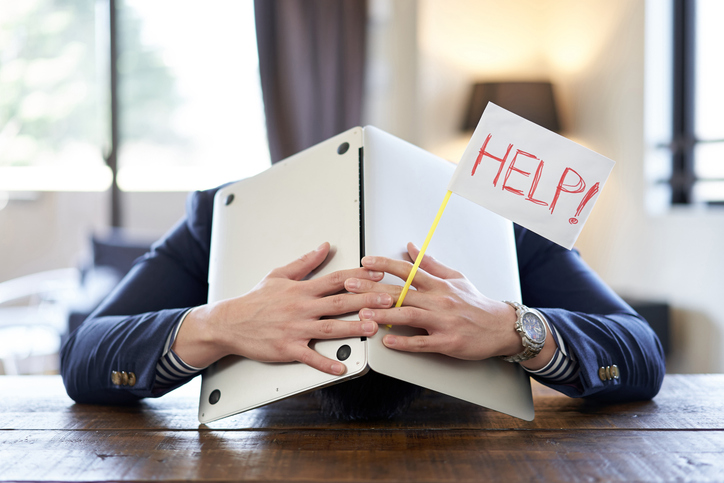
コロナ禍以降、仕事に対する概念も徐々に変化してきている日本社会。
仕事や所得も大切ですが、それ以上に自分自身の人生を大切にする考え方も浸透しつつあり、高度経済成長期のような「寝るのは悪」的な文化は、すでに時代錯誤となりつつあります。ただ、一方でデジタル社会は加速度的に進歩を早め、個々のメンタル起因の不眠は取り残されつつあるのも実情。
仕事の不安や悩みで寝れなくなるのはストレス耐性が低いから
などと評価する向きもあり、なかなか根本的な問題解決には至りにくく、また個々にその要因を押し付けている節が感じられるのが実情かもしれません。
なお、入眠障害や途中覚醒など、不眠症で悩む人の割合については
- 入眠困難:約30~35%
- 中途覚醒:約45~50%
- 早朝覚醒:約10~15%
- 熟眠障害:約10~20%
出典:国立精神・神経医療研究センター
「睡眠障害ガイドライン わが国における睡眠問題の現状」
https://www.ncnp.go.jp/nimh/behavior/phn/sleep_guideline.pdf?utm_source=chatgpt.com
となっており、年齢分布で言うと
20~30代:入眠困難&中途覚醒
40~50代:中途覚醒&早朝覚醒
といった具合に、世代によって不眠の質が変わってくるのが特徴です。
40~50代における途中覚醒については、加齢に伴う夜間頻尿なども含まれてきますので、詳細は「▼40代の1/8が頻尿?中高年から始まる頻尿の予防と対策」も併せて参考にしていただければと思いますが、
20~30代ほど生活習慣のリズムや行動習慣の影響が出やすい
40~50代ほど加齢による睡眠リズムの変化や社会的ストレスの影響が出やすい
という傾向があります。
言うなれば、年を重ねるほど社会的に責任が重くなり、悩みやストレスも増えるということになりますので、それら社会的なストレスを軽減するためにはどうすれば良いかを考える必要があります。具体的には、「認知アプローチ・行動アプローチ・環境アプローチ」の3軸が、広く一般的に用いられるストレス軽減法となり、
●認知アプローチ
自身でストレス要因となっている事柄を整理して、自身で解決できるものと自身で解決できないものを切り分ける。ストレスを認知する作業。整理できそうな問題・課題から解消の道筋を立てて行動計画を立てる。
●行動アプローチ
生活習慣の見直しや変化を与え、これまで行っていなかった運動習慣や気分転換を取り入れる。特に軽いジョギングなどがオススメで、身体の疲労感から睡眠の質も向上、良質な睡眠を得ることでストレス耐性も向上します。
●環境アプローチ
労働時間など、現在の生活環境を変える取り組み。生活パターンを変えたり、就寝環境を変えたり、部屋の模様替えなどをすることも効果的。人間関係については社会的アプローチとなりますが、環境を変えるという観点では違った人との付き合いもまた変化を与えるきっかけとなります。
上記のように、30~50代に最も多い心理的要因(メンタル)の不眠においては、
そのストレスの元凶が解消できずに不眠が長引く
という傾向にありますが、すぐにその元凶が解消できない場合、自身ではその原因が変えられない場合など様々なケースがありますので、まずはストレスの原因をしっかりと切り分けて認知すること、それに対してどのような行動が取れるか?を自身で認識することから始めるのが良いでしょう。
自身の感情を整理して、その解決の道筋を立てることで「ストレスを軽減できることもある」ということを覚えておきましょう。
当サイトに掲載されている情報は、一般的な健康・医療に関する知識や生活習慣などの改善のヒントを提供することを目的としております。本サイトの情報は、診断・治療・処方を目的としたものではありません。体調や症状に関する判断は、必ず医師や薬剤師、管理栄養士などの専門医・専門家にご相談ください。 なお、本サイトの情報に基づく行動や判断によるいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。掲載情報は可能な限り最新かつ正確な内容を心がけていますが、予告なく変更・修正する場合がございます。