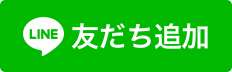最大のインナーケアは自律神経~ホルモンバランスを整えることの重要性
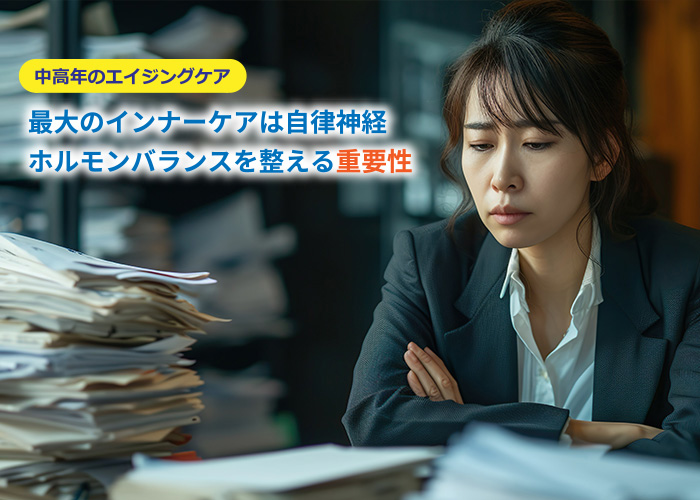
いま注目の「ホル活」~加齢と自律神経の変化の相関性を知ろう
昨今注目度が高まっている中高年のインナーケア。
アンチエイジングも、シミやシワといった外見面でのスキンケアだけでなく、体の内側からのエイジングケアの重要性が徐々に浸透しつつありますが、なかでもその意識が高まってきているのが
自律神経やホルモンバランスを整えること
巷では「ホル活」とも言われますが、特に更年期を控えた中高年女性においては、加齢による更年期症状でホルモンバランスが乱れやすく、その影響で自律神経も乱れて心身不調になりやすいことから、まずはその部分を整えて健康的な日々を過ごそうという機運が高まっているのです。
もちろん更年期症状は男性にもありますが、特に女性の更年期症状においては、女性ホルモンが急激に減少することによる体の変化が大きく
- 見た目の加齢変化
- 気分の浮き沈みやイライラ
- 動悸・めまい・ホットフラッシュ
- 高血圧や甲状腺疾患
- 不眠や夜間頻尿
などなど
日常生活においても常にストレスになるような体の変化に見舞われやすいことは、過去記事「▼女性の尿漏れと更年期・閉経との相関性」でもご紹介したとおりで、言わずもがな男性以上に自律神経が乱れやすい状況になりやすい傾向にあります。
こうして冷静に考えると、自律神経を整えることで知られる「ヨガ教室」に通うのは
女性の方が圧倒的に多いのも理に適っている
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「ヨガ教室アンケート調査」
https://j-net21.smrj.go.jp/startup/research/service/cons-yoga.html
と言えるかもしれませんが(日本限定ではありますが・・・)、加齢によってホルモンバランスが乱れ、ホルモンバランスが乱れることで自律神経も乱れ、体のあらゆる箇所で不調を来すとなると、やはり大元である加齢による体の変化を最小限に抑え、ホルモンバランスを整える
「ホル活」の重要性は今後ますます高まる
ものと思われます。
そこで今回の記事では、そんな中高年女性が直面する「自律神経の乱れからくる体の不調」を少しでも抑制すべく、エイジングケアの一環として
自律神経・ホルモンバランスを整える
をテーマに、まずは自律神経やホルモンバランスの基礎知識から、具体的な整え方までを詳しくご紹介していきます。年を重ねるごとに価値観が変化するように、20~30代は外見的に綺麗でいたいという気持ちが強くても、40~50代以降の方の多くは
外見より内側から綺麗で健康でいたい
という気持ちが高まりますので、その意識を保つためにも加齢による体の変化はもちろんのこと、それによるホルモンバランスや自律神経の乱れのメカニズムをしっかりと把握しておく必要があります。今回は、そんな自律神経を整えるインナーケアについて深堀して見ていきましょう。
自律神経が原因のストレス耐性低下が招く体の不調・変調

早速ですが、自律神経を整える必要性を具体的に見ていきましょう・
その前に、ホルモンバランスだの自律神経だの、よく聞く言葉ではありますが、体内におけるそれぞれの役割や関係性などについて詳しく見ておきましょう。
≪ホルモンバランス≫
特定のホルモン同士の比率や分泌量のバランスを指します。
女性の場合は主に
- エストロゲン
- プロゲステロン
- テストステロン
- 卵胞刺激ホルモン
- 黄体化ホルモン
の比率を指します。
男性の場合は、テストステロン・ジヒドロテストステロン・エストロゲンのほかストレスホルモン「コルチゾール」なども含まれてきます。
≪自律神経≫
自分の意思とは関係なく働く神経系機能
- 活動時に優位となる交感神経
- 安静時に優位となる副交感神経
で構成されます。
自分の意思とは関係なく働く神経系機能と言われてもピンと来ないかもしれませんが、例えば暑ければ自分の意志に関係なく汗をかく、走れば呼吸が早くなり心拍数が上がる、寒いと震えて体温を上げようとする、こうした機能はすべて交感神経と副交感神経による働きです。
こうしてみると、ホルモンバランスの乱れと自律神経の乱れは、あまり相関性がないようにも見えますが、
実は機能的に重なり合う部分が非常に多く
互いに影響し合う機能ではあります。分かりやすく言うと、
- 自律神経が乱れるとホルモンの分泌も乱れる
- ホルモンバランスが乱れると自律神経も乱れる
という特性がありますので、一心同体と言っても過言ではありません。
前述のとおり、中高年女性においては加齢による女性ホルモンの分泌減少によって、まず最初にホルモンバランスが乱れます。特に幸福ホルモンとも呼ばれるエストロゲンが減少することで、
気分が不安定になったり、不安やイライラの原因となります。
その他にも、プロゲステロンは体温を上昇させる作用があったり、血管を拡張させたりと、ホルモンバランスの変化・乱れは精神面の影響だけに留まりません。
ホルモンバランスが乱れると、次に影響を受けるのが神経伝達物質です。
エストロゲンが減少することで、神経伝達物質であるセロトニンも低下してしまいます。セロトニンの働きについては、過去記事「▼体内時計をつかさどるメラトニンの働きを理解しよう」などを参照していただければと思いますが、セロトニンは活動ホルモンであると同時に交感神経のブレーキ役でもあるため、これが減少することで
ホルモンの指令と体の反応にズレが生じてくる
ことで、血圧が上昇しやすくなったり心拍数の増加、不眠や不安、イライラといったように自律神経に影響を及ぼしてくるというメカニズムです。この交感神経の抑制がきかなくなることで、体のなかではストレス耐性が低下して
- イライラしやすくなる
- 動悸や息切れなどが起こりやすい
- 肩こりなど慢性的な痛み
- 良質な睡眠が取りにくくなる
- 不調がストレスとなり情緒不安定
といった具合に、さらにホルモン分泌のリズムを乱す悪循環に陥りがち。
つまり、ホルモンバランスを整えることが結果的に自律神経を整えることになるのです。ただし、個人差はあれど中高年女性の閉経前後は、大きくホルモンバランスが変化する時期でもあり、エストロゲンの減少は避けられません。
よって、ホルモンバランスを整えるためにも自律神経の乱れを最低限に抑え、ストレスや不安に支配されないような習慣を身に付けることがポイント。その方法のひとつとして、エストロゲンに似た成分である「大豆イソフラボン」を意識的に摂ったり、30分程度の入浴でリラックスしたりして、良質な睡眠を得ることも自律神経を整えるには効果的です。
「中高年のエイジングケア」に関する人気記事
インナーケアに全振り?!中高年のエイジングケアはバランス重視

更年期前後の中高年女性の自律神経が乱れやすい原因を理解したところで、実際にそれらを抑制するためには「どのようなことを心がければ良いのか?」という核心部分について見ていきましょう。
前段でも解説したとおり、ホルモンバランスの変化は避けられませんし、それによる自律神経の乱れもある程度は避けられない部分でもあります。ただし、ストレスは日々の入浴などによってある程度緩和できますし、不眠においても適度な運動習慣によって体を疲労させることで、良質な入眠を誘うこともできるのです。
ただ、世の中の中高年女性の実情を見れば
- ゆっくり入浴する時間がない・・・
- ウォーキングする時間が取れない・・・
- それがまたストレスの原因になる・・・
というのが現実で、そういう意味では、仕事に出ている男性の方が自分の時間を取りやすいのかもしれませんが、
家族に協力をお願いして自分時間を作る
というところから始めてみても良いかもしれません。
冒頭でもお伝えしたように、ホルモンバランスと自律神経は重なり合う部分が多い一方、それぞれを整えるアプローチは若干異なりますので、基本的な整え方を軽く見ておきましょう。
1,自律神経を整える方法
・自律神経を整えるとは、交感神経と副交感神経の働きを整理すること
・自律神経を整えるには良質な睡眠、適度な運動、リラックス、規則正しい生活
・生活習慣を見直し、生活リズムを整えることが大前提
2、ホルモンバランスを整える方法
・ホルモンバランスを整えるとは、生理周期や代謝、ストレスなどを調整すること
・ホルモンバランスを整えるには、栄養・睡眠・運動・ストレス環境の見直し
・自律神経同様、生活習慣を見直すほか過度なストレスを抑制することが肝要
このように、ホルモンバランスを整えるにせよ、自律神経を整えるにせよ、日常生活のなかである程度対処できる内容であり、ちょっとした意識ひとつで、乱れたリズムを改善することができるのです。
- 規則正しい生活習慣
- バランスの取れた栄養
- 良質な睡眠と睡眠時間
- 適度な運動と入浴・サウナ
まぁ、「言われなくても分かってます!」と思われる方がほとんどかもしれませんが、特に自律神経の乱れは、更年期前後の中高年女性に限らず、PMSなどによってホルモンバランスが乱れたり、夏場のエアコンなどでも乱れやすくなったりする傾向にあります。また、仕事のストレス、睡眠不足などは自律神経の乱れに直結しますので
体内のバランスを維持することを心がけ
規則正しい生活習慣を乱さないようにすることが重要です。
例えば、メンタルが疲れていると感じる時には、軽く運動をして肉体も疲れさせることで良質な睡眠を得やすくなりますし、ストレスを飲酒で紛らすような習慣は、その場は良かったとしても根本的な解決にならず、
余計体調を悪化させる恐れがある
ということを留意しておきましょう。
当サイトに掲載されている情報は、一般的な健康・医療に関する知識や生活習慣などの改善のヒントを提供することを目的としております。本サイトの情報は、診断・治療・処方を目的としたものではありません。体調や症状に関する判断は、必ず医師や薬剤師、管理栄養士などの専門医・専門家にご相談ください。 なお、本サイトの情報に基づく行動や判断によるいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。掲載情報は可能な限り最新かつ正確な内容を心がけていますが、予告なく変更・修正する場合がございます。