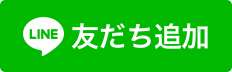40代の1/8が頻尿?中高年から始まる頻尿の予防と対策
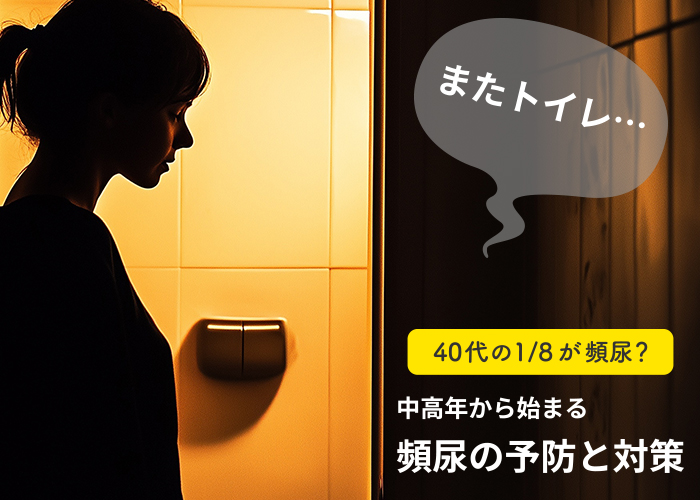
中高年の頻尿原因の多くは生活習慣と加齢起因の後天的要因
中高年以降、加齢による体の変化として実感度の高い症状のひとつが「頻尿」。
トイレの回数が増えたり、一度の排尿の量が少なかったり、就寝中に必ずトイレで目が覚めるといった症状が代表的ではありますが、40~50代からの頻尿においては膀胱の柔軟性低下や骨盤庭筋の筋力低下など、さまざまな要因が重なって起こる加齢変化のひとつです。
白髪が増えるのと同じくトイレも近くなる
と聞けば、頻尿も身近に感じるかもしれませんが、排尿頻度については多少なりとも日常生活に影響を与える可能性がありますので、白髪やシミ・シワといった加齢起因の外見的変化とは、ちょっと性質が異なるものであることは言うまでもありません。
過去記事「▼40代以降はみんな悩む~アラフォー世代の尿漏れの実態」でもご紹介しているように、中高年世代ともなると、男女問わず多くの人が頻尿や尿漏れを体感・体験しており、その割合は
- 40代男性で約15~20%
- 40代女性の約20~30%
- 50代男性の約20~25%
- 50代女性の約30~35%
が、頻尿や尿漏れの悩みを抱えていると言われています。
https://www.urol.or.jp/public/symptom/02.html
なお、頻尿の定義については「▼飲酒後の朝は尿漏れしやすい?お酒と尿量と尿漏れの関係」の記事で詳しく紹介しておりますが、一日の排尿回数が8回以上という頻尿の定義は少々漠然とした部分があり、例えば
- 1日の排尿総量が約1,500ml(平均値は1,000~2,000ml)
- 1日の排尿回数が約8回(それ以上は頻尿と定義)
- 1回の排尿量が約200ml
という計算になりますが、仮に排尿総量が3,000mlあった場合
- 1日の排尿総量が約3,000ml
- 1回の排尿量が約200ml
- 1日の排尿回数が約16回
トイレの回数としては16回となるので、定義的には「頻尿」ではありますが、1回の排尿量が約200mlと正常であるため、
この場合は頻尿ではなく「多尿」という症状
ということになり、必ずしも泌尿器に何か問題がある訳ではありません。
日によっては、一日の水分摂取量が多かったり、ストレス状況や生活習慣の乱れなどによる一時的な生理的現象である場合もありますので、トイレの回数だけで頻尿を判断するのはナンセンスである、ということも覚えておくと良いでしょう。
そこで今回の記事では、そんな中高年の多くが直面する「頻尿」をテーマに、
加齢症状ならではの予防対策をご紹介
老眼や白髪などと同様、老化現象だから仕方ないと割り切る部分も必要ですが、特に夜間頻尿は、睡眠の質を大きく低下させ、寝ているのに疲れが取れなかったり、翌日の活動時間中のパフォーマンス低下にもつながりますので、頻尿とは言え、日常生活にも悪影響を与えかねない機能低下減少なのです。
頻尿を十分に理解し、生活習慣の改善などの予防対策することで、ある程度は頻尿を抑えられるかもしれませんので、この記事で正しい知識を身に付けてしっかりと頻尿対策を行っていきましょう。
生活の質に悪影響を及ぼす「夜間頻尿」とどのように向き合うか?

頻尿においては、言うまでもなく個人差が大きい点もありますが、なにより
プライベートでデリケートな領域
であることから、あまり話題にならないことが予防や対策が後手にまわる原因のひとつと言えます。そのため、頻尿に対する誤った知識が先走りしてしまい、多くの方の認識として「トイレの回数」という点に注目されがち。前段の例でもお伝えしているとおり、1回の尿量平均が約200~300ml前後だとすると
50~100ml程度まで減少すると頻尿
と診断される可能性があり、加齢による膀胱の柔軟性の低下や、骨盤底筋の緩みなどは、まさに1回の排尿量が減少する要因となります。中高年による頻尿傾向は、ある程度生活習慣との関連性もあり、皆さんが良くご存じの
利尿作用の高いお茶やコーヒーなどのカフェイン摂取
はもちろんですが、それ以外にも
- 体内の水分保持を増やす塩分の摂りすぎ
- 膀胱の感受性を高めるアルコールの摂取
- 中年太りによる腹圧上昇(膀胱圧迫)
なども頻尿原因となり、生活習慣とも大きな密接関係にあります。
日中の活動時間においては、トイレの回数が増えるだけで、頻尿を意識することはあまりないかもしれませんが、これが夜間になると話は別。「▼頻尿で熟睡できない?!朝までトイレに行かずに眠るには」でもお伝えしているとおり、基本的に就寝中に1回以上排尿のために起きれば夜間頻尿に定義されますので、日中の排尿回数対策はもちろんですが、
それ以上に夜間頻尿対策&予防が重要
という認識を持つことが大切です。
https://www.urol.or.jp/lib/files/other/guideline/
37_nocturia_v2-2.pdf
ただ、ひと言で「夜間頻尿対策」と言っても、生活習慣のなかで出来ることもあれば、加齢による体質変化で対応できない部分もありますので、ご自身で対策が取れることと取れないことをしっかりと切り分けし、
夜間頻尿を引き起こす原因を明確に把握する
ことから始めてみましょう。
例)
1,加齢による生理的変化
腎機能の低下や▼抗利尿ホルモン(ADH)の減少などは生理的変化となるためコントロールが難しい。
2,就寝前の摂取水分コントロール
就寝前のアルコールやカフェインの摂取は、睡眠の質を低下させるだけでなく、抗利尿ホルモンの機能低下も招くことで尿意を催しやすくなります。夕食は塩分摂取をできる限り減らし、就寝2時間前くらいから水分摂取を控えるなど、ある程度自身でもコントロールすることができます。
3,SASは過活動膀胱、前立腺肥大などの疾患
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、単に眠りが浅くなって排尿感を感じやすくなるだけでなく、呼吸が減ることで胸腔内の圧が下がり、心臓に血液が戻りやすくなり、それにより心臓からは利尿ペプチド(ANP) が分泌されることで、腎臓で産生される尿が増えやすくなります。SASの主な原因が肥満なので、生活習慣や食生活を見直すなど、こちらも自身でコントロールが可能な範囲です。
このように、夜間頻尿と聞くと何かの疾患のように聞こえますが、要するに
不規則な生活習慣や食生活の乱れ&運動不足
に起因する部分も多いため、その見直しと改善から対策するのが良いでしょう。
上記2番や3番のように、自身でコントロールできる部分は可能な限り抑制すること、1番のような加齢・老化起因の体の生理的変化については予防が難しいため、予防という観点ではなく、機能低下を抑制・遅らせるという視点で、膀胱トレーニングや骨盤底筋トレーニングを取り組むと良いでしょう。
「中高年の頻尿対策」に関する人気記事
取れる対策は限られる?~生活習慣と睡眠時間が頻尿と大きく関連する理由

前段でもお伝えしたように、夜間頻尿に限らず、頻尿対策として行えることは思いのほか多くありません。頻尿予防に限らず、健康維持の大前提となる規則正しい生活・栄養バランスの取れた食事・適度な運動、そして良質な睡眠が予防対策となることは言うまでもありません。
ただ、冒頭では「膀胱の柔軟性低下や骨盤庭筋の筋力低下が頻尿の原因のひとつ」とお伝えしており、だとすると尚更、不可避な生理的変化であり、いくら水分摂取量を抑制しても、規則正しい生活を心がけても、あまり意味がないようにも思えます。つまり、
生活習慣と睡眠時間と頻尿の相関性がイマイチ不明
ということでもあります。
そもそも尿を溜める膀胱の柔軟性が低下して膀胱容量(蓄水量)が減るため、頻尿は致し方ないという考えが一般的かもしれませんが、実際には尿が作られるメカニズム、そして尿意を催すメカニズムは、腎臓や膀胱・神経などが連携する非常に複雑な仕組みです。当然、膀胱の柔軟性や蓄水量だけで尿意が決定される訳ではありませんので、一つずつ整理しながら、生活習慣や睡眠時間との相関性を見ていきましょう。
1,生活習慣と頻尿の関係性
概ね想像のとおりかもしれませんが、中高年以降に多い肥満や高血圧をはじめとする生活習慣病。筋量が減少し、基礎代謝が落ちはじめる40~50代の多くは、自然と脂肪が増えやすくなり、肥満気味になる傾向にあります。肥満と頻尿との相関性を見ると
- 睡眠時無呼吸症候群の原因となる
- 肥満の人は相対的に塩分や脂の多い食事
- 内臓脂肪の増加による膀胱・尿道の圧迫
- 肥満の多くは運動不足で骨盤底筋などの筋力も低下
つまり、頻尿になる素地が整っていると言っても過言ではありません。
ちなみに、肥満は夜間頻尿の主な危険因子の1つで、
BMIが25以上は夜間頻尿の発症率が高くなる傾向
と、国際禁制学会(ICS)は調査レポートを公表しています。
https://www.ics.org/Abstracts/Publish/43/000163.pdf
2,睡眠時間と頻尿の相関性
上記の肥満と関連する部分もありますが、睡眠時無呼吸症候群は睡眠の質を大幅に低下させることで、実際に寝ていても寝不足のような状態になります。これによって影響を受けるのが、上述いたしました抗利尿ホルモン(ADH)で、SASや睡眠不足などにより分泌リズムやサイクルが乱れることで夜間頻尿が起こりやすくなります。睡眠と頻尿の相関性を見てみると
- 抗利尿ホルモン(ADH)の分泌サイクルが乱れる
- 質の低い睡眠や睡眠不足だと交感神経が優位になりやすい
- 睡眠不足によって自律神経を乱れ膀胱感受性が増加する
膀胱感受性とは、分かりやすく言えば尿意の感じやすさで、
尿が溜まって膀胱が少し膨らんだだけで強い尿意を覚える
ということになります。
例えば、部屋の電気を煌々と点けたまま寝ても、夜中に目が覚めてしまうのと同じように、就寝中にもかかわらず交感神経が優位だと夜中に覚醒しやすく、抗利尿ホルモンの分泌もままならないため、尿が作られやすくなり夜間頻尿になりやすい傾向にあります。そもそもの寝不足は論外ですが、
就寝環境を整える重要性は頻尿対策にも影響があるのです
就寝環境の最適化については、「▼寝つきが悪い原因は?布団や枕を見直して熟睡環境を整えよう!」なども参考にしていただければと思いますが、これらのように生活習慣と睡眠環境は、頻尿の一要素として非常に大きなウェイトを占めておりますので、頻尿対策への意識を高めるうえで
規則正しい生活習慣(運動含む)と良質な睡眠
は、切っても切れない要素のひとつなのです。
いかがでしたでしょうか?
まさか頻尿と塩分摂りすぎが関係しているとは思いもしなかったかもしれませんが、排尿や尿意は、身体の様々な器官や神経とが連携した複雑な生理現象でありますので、そこを完全にコントロールすることはできなくとも、ある程度抑制できるよう、正しい知識と高い意識を持つよう心がけましょう。
当サイトに掲載されている情報は、一般的な健康・医療に関する知識や生活習慣などの改善のヒントを提供することを目的としております。本サイトの情報は、診断・治療・処方を目的としたものではありません。体調や症状に関する判断は、必ず医師や薬剤師、管理栄養士などの専門医・専門家にご相談ください。 なお、本サイトの情報に基づく行動や判断によるいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。掲載情報は可能な限り最新かつ正確な内容を心がけていますが、予告なく変更・修正する場合がございます。