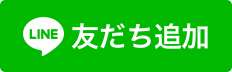睡眠時間は無関係?!良質な睡眠の特徴と不眠症の改善方法

睡眠の質が低下しやすい中高年以降の体の変化と特徴
主に健康への意識が高まる40代以降において、食事や栄養バランスに気を付けたり、運動習慣を身に付けたりする方が多い一方、健康維持という観点ではあまり意識されることがないのが「睡眠」です。睡眠の重要性においてはなんとなく理解しているものの、多くの方が
睡眠不足だとパフォーマンスが低下する
という意識程度に留まっており、「睡眠不足=睡眠時間の不足」という認識しかないのが実情かもしれません。たしかに、現代社会においては「睡眠負債」という言葉があるように、慢性的な睡眠不足で心身に様々な悪影響を及ぼしていることが社会問題になりつつありますが、昨今では
十分な睡眠時間を取っているのにパフォーマンスが低下する
という傾向が特に中高年に顕著となりつつあり、睡眠時間の長短より、睡眠の質が重要だということが意識されはじめております。多くの方が実感する「若い頃はいくらでも寝れたのに、年を取ると寝るのもたいへん」という状況について、なぜ中高年以降になると眠りが浅くなってしまうのか?という点については
・筋量が減少して基礎代謝が低下、必要な睡眠時間が短くなる
・加齢を背景に睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌量が減少する
・女性の場合、エストロゲンの急激な減少やホルモンバランスの変化
などが挙げられ、
言わば睡眠の質の低下は一種の加齢現象
である以上、短くなる睡眠時間とも上手に付き合っていく必要があることは、過去記事「▼一番寝れない年代は40代?ストレスと睡眠時間の関連性」でもご紹介したとおりです。
そこで必要になってくるのが「短い睡眠時間でもしっかりと睡眠効果を得ること」であり、10代~20代の時のように、何時間でも寝続けるということが難しい以上、
短い睡眠時間のなかでいかに効率のよい良質な睡眠を取るか?
ということも重要な要素となってくることは言うまでもありません。
これまで睡眠時間という時間軸でしか睡眠を捉えてこなかった方においては、より多くの睡眠時間を確保しようとするかもしれませんが、結果的に
質の低い睡眠時間を増やしても睡眠効果は得にくい
ということが言えますので、個人差はあれど中高年以降は、睡眠の長さより睡眠の質にフォーカスして、相対的に短時間であっても「よく寝れた~」と感じられるような睡眠が取れるよう、生活習慣を整えたり就寝環境を整備したりすることが肝要です。
この記事では、そんな中高年以降に低下しやすい睡眠の質と、その対策を中心に日常生活での留意点などをご紹介していきます。上記のとおり、40代以降は加齢によって体に様々な変化がみられるなか、
睡眠の質の低下だけでなく不眠にもなりやすい傾向
やはり良質な睡眠を確保するためには、規則正しい生活習慣や栄養バランスだけでなく、ストレスをコントロールして自律神経を整えたり、心身をリラックスさせるために様々な対策を講じる必要があります。特に個人差が顕著となるメンタル要素も深く関わってきますので、
「眠れない=睡眠不足」ではない!不眠症と睡眠の質との関係性

睡眠をより深く理解するためには、睡眠の量と質の違いを理解する必要があります。
一般的には、寝不足や睡眠不足と言うと「睡眠時間が足りない」というイメージ。また、不眠症においても「寝つきが悪い・すぐに目が覚めてしまう」といったように漠然としたイメージで、言葉だけが独り歩きしてしまっている面もあります。
睡眠不足とは「十分な睡眠が取れずに活動時間帯に眠気や倦怠感などが生じること」ではあり、上記認識が間違えている訳ではありませんが、中高年以降に増える
十分な睡眠が取れているのに活動時間に眠気や倦怠感などが生じる
といった状態ですと、解決策は
「睡眠時間を確保すること」ではなくなる
ということは言うまでもありません。
また、不眠症においては「▼睡眠障害ってどんな症状?寝れない時の睡眠障害セルフチェック」でも詳しくご紹介しているように、その不眠の状態に応じて原因も対策も異なってくるので、不眠症は睡眠障害の総称であることを認識しておく必要があります。
睡眠の量と質においては、仕事に置き換えると分かりやすいのですが
・仕事の量は多くこなす一方、ミスが多く仕事の質は低い
・仕事の量は少ないが、内容が完璧で仕事の質が高い
前者は主に若い世代に多く、後者は逆に経験豊富な熟練者に多い傾向にあり、まさに睡眠の量と質の関係と同じであることが言えます。つまり、経験豊富な熟練者(中高年以降)ほど、睡眠の「量は少なくとも質が高い必要がある」ということであり、
睡眠の量(時間)も少なく質も低い
という状態では、睡眠不足どころか日中の活動に支障が出てしまうことは必至です。
よって、不眠症という睡眠障害を患っている状況では、当然質の高い睡眠を得ることはできないため、必然的に睡眠不足(良質な睡眠が得られない)になるという関係性になるのです。不眠の原因においては、心理的要因や身体的要因以外にも様々な原因がありますので、一概に言えない部分がありますが、
良質な睡眠を得るためには不眠要因を解消する
ことが前提となり、自分自身の不眠原因を把握・認識してその対策を講じていくことから始める必要があります。
不眠要因には、心配事や悩みであったり、夜中にトイレに起きてしまう夜間頻尿であったり、肥満によるSAS(睡眠時無呼吸症候群)であったりと、様々な原因が内在しておりますので、単に睡眠の質を高めようと意識するのではなく、逆に良質な睡眠の阻害要因を解消しよう!というアプローチで対策を講じていくよう心がけましょう。
「良質な睡眠と不眠症」に関する人気記事
不眠の原因は肥満?!浅くなる眠りを改善する生活習慣のイロハ

この記事では、主に中高年以降の睡眠の質の低下にフォーカスしておりますが、中高年からの睡眠の質の低下は、ある意味加齢症状のひとつであり、加齢による体の変化が睡眠の質の低下要因となっているため「対策の講じようがない」とも取ることができます。
老化現象には、老眼であったり、基礎代謝の低下、筋肉量の減少など、個人差はあっても様々な変化が見られるようになり、特に睡眠の質に影響を及ぼしやすい加齢症状が、
体の糖化とホルモンバランスの変化
で、筋肉量の減少と糖化によって脂肪が蓄積されやすくなる、つまり肥満になることでSASを引き起こしやすくなったり、いびきをかきやすくなることで自身の睡眠の質だけに留まらず、
寝室を共にしているご家族の睡眠の質も低下させてしまう
可能性すらあります。
ホルモンバランスの変化は、主に女性に対して大きな影響を与えるほか、脂肪を蓄えやすくなる、筋量が減りやすくなるといった点も女性に多い傾向にありますので、不眠が女性に多い傾向にあることは、まさに上記要因などが影響していると考えられます。なお、脂肪が増えやすくなるという点は男女問わずではありますが、
肥満と良質な睡眠は相関性があることが明らかになっており
質の高い睡眠が十分に取れていないと糖尿病のリスクが高まるほか、食欲を抑える抗肥満ホルモン「レプチン」が低下、逆にグレリンという食欲増進ホルモンが増加してしまうことは「▼睡眠不足が招く仕事のパフォーマンス低下と性格の変化」でもご紹介しているとおりです。中高年における睡眠の質の低下までのプロセス例を簡単に見てみると
代謝低下など、加齢によって肥満になりやすくなる
↓
筋力の低下などでいびきをかきやすくなる(SASの兆候)
↓
睡眠の質が低下して慢性的な睡眠不足状態になる
↓
良質な睡眠が取れずにホルモンバランスが崩れ食欲が増進
↓
さらに肥満が進行して、より睡眠の質が低下してしまう
上記は一例ではありますが、このような流れは決して他人事ではなく誰しも起こりうることなのです。上記のように、加齢に伴う体の変化に対応し、浅くなる眠りを改善するには
・睡眠時間は十分取るよう心がける
・夜中にトイレで目が覚めないよう水分を控える
・適度な運動習慣によって体を疲れさせる
・栄養バランスとの取れたカロリー控えめの食事
・基礎代謝を高めるための筋力アップトレーニングを取り入れる
といったことを習慣化させることで、加齢症状が顕著化した中高年の体の変化に対処することができるようになります。加齢による肥満については、睡眠の質に直接悪影響を及ぼすというより、首回りや咽喉部周辺に脂肪がついて気道を圧迫し、いびきをかきやすくしてしまいますので、結果的に
肥満が睡眠の質に直結してしまう
ということを留意しておくことがポイントと言えるでしょう。
不眠や睡眠の質の低下は様々な要因がありますが、加齢症状は避けることができませんので、自身でもできる運動習慣を身に付けたり、高カロリーな食事の抑制、規則正しい生活など、肥満要因を極力抑えることで、結果的に「睡眠の質を低下させないことにつながる」ということを心に留めておくようにしましょう。
当サイトに掲載されている情報は、一般的な健康・医療に関する知識や生活習慣などの改善のヒントを提供することを目的としております。本サイトの情報は、診断・治療・処方を目的としたものではありません。体調や症状に関する判断は、必ず医師や薬剤師、管理栄養士などの専門医・専門家にご相談ください。 なお、本サイトの情報に基づく行動や判断によるいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。掲載情報は可能な限り最新かつ正確な内容を心がけていますが、予告なく変更・修正する場合がございます。